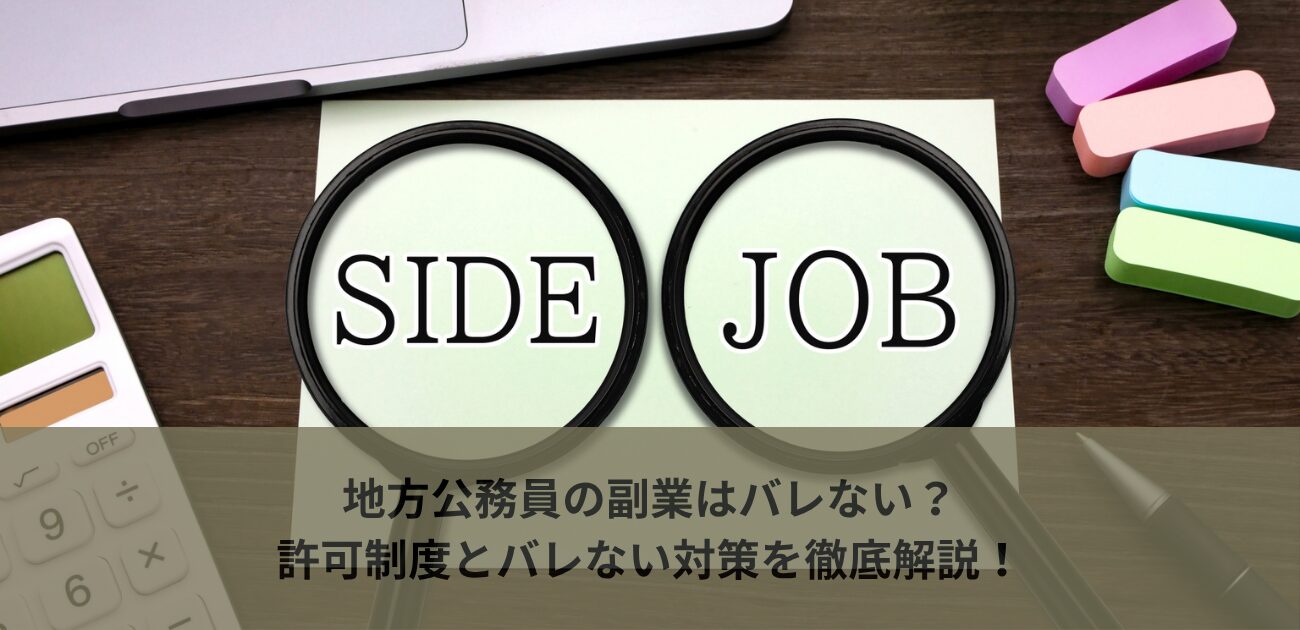副業に関心がある地方公務員の方にとって、「副業はバレないのか?」という疑問はとても重要です。
生活費の補填やスキルアップのために副業を検討する方も増えていますが、公務員には特有のルールがあるため、慎重な判断が求められます。
この記事では、副業が禁止されている理由や許可制度、そしてバレないための現実的な対策について、わかりやすく解説していきます。
地方公務員が副業を禁止されている4つの理由とは?法律とルールを解説
地方公務員が副業を自由にできないのには、明確な法律上の根拠と公務の性質が関係しています。
特に公務員という立場上、住民からの信頼を損なうことなく職務を全うする必要があるため、副業に対して厳しい制限が設けられています。
以下では、具体的な理由について順番に説明していきます。
理由①:国家公務員法と地方公務員法で副業が制限されているから
国家公務員と地方公務員のいずれにも、「営利企業への従事等の制限」が設けられています。
地方公務員法第38条では、公務員が許可なく営利を目的とする事業を行ったり、他の職を兼ねることを禁止しています。
この法律は、たとえ本業に影響が出ていなくても、営利活動そのものを制限するため、副業を始めるには許可が必要になります。
ルールを破ると懲戒処分の対象にもなり得るため、十分な注意が必要です。
理由②:副業が公務の信用や公正性に影響を与える可能性があるから
地方公務員は、公平性と中立性が強く求められる職業です。
もし副業によって特定の業界や企業との利害関係が生じれば、住民からの信頼が損なわれかねません。
たとえば、副業先が公共事業に関わっていた場合、利益相反とみなされる可能性もあります。
そのため、どんなに小さな仕事であっても、公務の信用性を揺るがすような活動は制限されるのです。
理由③:住民サービスに支障をきたす恐れがあるから
副業に時間や体力を割きすぎると、本来の業務に悪影響が出る可能性があります。
住民に対する対応が遅れたり、業務の質が低下すれば、それは直接的に地域社会のサービス低下につながります。
地方公務員には、地域住民の暮らしを支えるという重要な役割があるため、職務に専念できない副業は問題視されがちです。
このようなリスクを回避するためにも、副業には厳しい制限が設けられています。
理由④:公務員としての職務専念義務が求められているから
地方公務員法第30条では、「職務に専念する義務」が明記されています。
これは、勤務時間中はもちろん、勤務外であっても本来業務に影響が出るような活動を控えるべきという考え方です。
副業によって心身が疲弊すれば、翌日の業務に集中できなくなる可能性もあります。
また、職場の同僚との連携やチームワークにも影響を与えることがあり、公務の円滑な運営に支障をきたしかねません。
地方公務員の副業がバレるきっかけは何?実際によくあるバレ方5選
「こっそりやっているから大丈夫」と思っていても、副業がバレるきっかけは意外なところにあります。
特に地方公務員は住民に身近な存在であるため、ちょっとした情報から発覚するリスクが高いのが現実です。
ここでは実際によくある「バレた原因」を具体的に解説していきます。
バレるきっかけ①:住民税の申告内容からバレるケースが多い
副業がバレる最も典型的なケースが、住民税の申告によるものです。
副業で得た収入は確定申告が必要となり、その情報が市区町村に送られます。
公務員の住民税は通常「特別徴収」で給与から天引きされますが、副業収入によって住民税額が増えると、担当者が違和感を覚えて調査に至るケースがあります。
その結果、勤務先に副業が発覚するという流れが非常に多いのです。
バレるきっかけ②:同僚や知人からの密告で発覚することがある
意外と多いのが、職場の同僚や友人からの「密告」です。
副業していることを何気なく話してしまったり、SNSに投稿していたのを誰かが見つけたりすることで、噂が広まり発覚することがあります。
とくに公務員の職場では、副業に対する目が厳しい場合が多く、「ルール違反」と感じた人が上司に報告するケースも珍しくありません。
身近な人ほど情報源になりやすいため、言動には細心の注意が必要です。
バレるきっかけ③:SNSやブログで副業の情報を公開してしまうから
副業をしていることをSNSやブログで発信してしまい、それが原因でバレるというケースも少なくありません。
たとえば、ハンドルネームで運営していたつもりでも、写真やプロフィール、投稿内容などから個人が特定されてしまうリスクがあります。
特に副業内容に自信があるとついアピールしたくなる気持ちもわかりますが、公務員という立場上、情報発信は慎重であるべきです。
「誰にもバレない」と思っていたのに、思わぬところで繋がってしまうことがあります。
バレるきっかけ④:副業先の関係者が口外してしまうリスクがある
副業先の上司や同僚が、何気ない会話の中であなたが公務員であることを話してしまい、それが広まってバレることもあります。
特に飲食店やイベントスタッフなど、不特定多数の人と関わる仕事ではこのようなリスクが高くなります。
自分がいくら気をつけていても、他人の発言まではコントロールできません。
信頼できる関係者であっても、副業の内容や勤務先は極力伝えないようにすることが大切です。
バレるきっかけ⑤:税務署から市役所に情報が流れる可能性がある
確定申告をすると、その内容は税務署から市区町村に送られます。
その結果、住民税の課税内容が勤務先に通知され、担当部署が「副業収入がある」と気づく可能性があります。
特に地方公務員は、市役所や町役場が給与や税を管理しているため、内部で情報がつながりやすい構造です。
「申告しても大丈夫」と思っていても、意図せず情報が共有されてしまうリスクは常に存在します。
地方公務員のバレない副業は存在する?リスクの少ない副業の5選
「できれば副業をしたいけど、バレるのが怖い」という地方公務員の方は多いでしょう。
実際には、副業の種類によってバレにくさやリスクの度合いが大きく異なります。
ここでは、比較的バレにくいとされる副業や、その特徴について詳しく紹介していきます。
リスクの少ない副業①:匿名性の高いネット副業(ライティング・アフィリエイトなど)
ライティングやアフィリエイトなどのネット副業は、顔や名前を出さずに活動できるため、比較的バレにくい副業の代表です。
特にライティング案件はクラウドソーシングを通じて匿名で受注・納品が可能なうえ、作業は自宅で完結します。
また、アフィリエイトもブログやサイトを通じて収益化する仕組みなので、発信内容や個人情報の管理を徹底すれば、特定されるリスクを大幅に減らせます。
とはいえ、収益が一定額を超える場合は確定申告が必要になる点には注意が必要です。
リスクの少ない副業②:収入が少額で申告不要なポイントサイトやアンケートモニター
ポイントサイトやアンケートモニターといった「報酬が数百円〜数千円程度」の副業は、税務上の申告義務が発生しにくく、非常にバレにくい選択肢です。
これらは副業というよりも「お小遣い稼ぎ」に近い感覚で行えるため、公務員でも比較的安心して利用できる分野といえます。
ただし、あまりに多くのサービスに登録していたり、時間をかけすぎて本業に支障が出るようでは本末転倒です。
「スキマ時間に軽く取り組む」程度のスタンスで行うのがポイントです。
リスクの少ない副業③:趣味の延長としてのハンドメイド販売や写真素材の販売
アクセサリーや雑貨のハンドメイド販売、写真やイラスト素材の販売など、趣味を活かした副業も人気があります。
これらは「芸術活動」「創作活動」として認識されやすく、営利性が低いと判断されれば副業に該当しないケースもあります。
ただし、収益が増えれば営利活動と見なされる可能性があるため、稼ぎすぎには注意が必要です。
趣味の範囲にとどめながら、楽しみとして取り組むスタンスがベストです。
リスクの少ない副業④:家族名義で行う収益化活動
家族名義でブログやネットショップを運営し、収益を得る方法も検討されることがあります。
この場合、あくまで収益の主体は家族となるため、表面的には自分が副業をしているとは見なされにくくなります。
ただし、実質的に自分が運営していることが明らかになれば、名義貸しとみなされる恐れがあります。
万が一のトラブルを避けるためにも、家族の理解と協力、そして税務上のルールをしっかり守ることが重要です。
リスクの少ない副業⑤:自動化できる仕組みを使った不労所得型の副業
投資信託やロボアドバイザー、ストック型のコンテンツ販売など、労働を伴わない収益モデルも注目されています。
これらは「副業」というより「資産運用」に近いため、職務専念義務との関係も薄く、比較的寛容に見られる傾向があります。
ただし、FXや仮想通貨のようにリスクが高いものは、損失による精神的負担が業務に影響する場合もあるため、慎重に検討すべきです。
安定的かつ小規模に収益化できる仕組みを構築することが、バレない副業への近道と言えるでしょう。
地方公務員でも可能な副業の条件と許可が必要な4つのケース
副業が原則禁止されている地方公務員ですが、すべての活動がNGというわけではありません。
実は、営利性や公益性の有無、自治体からの許可の有無によっては、一定の副業や活動が認められるケースもあります。
ここでは、地方公務員が副業を行ううえで知っておきたい「許可が必要な場合」と「許可が不要なケース」をわかりやすく解説します。
ケース①:営利目的でなければ許可なく可能な活動もある
地方公務員法では、あくまで「営利を目的とする事業」や「営利企業等の役員兼任」などが禁止されています。
そのため、営利性がなく、報酬を伴わない活動であれば、原則として許可を得る必要はありません。
たとえば、地域のスポーツ指導や学校の部活動の手伝い、非営利の地域イベントへの参加などは、多くの自治体で問題視されていません。
ただし、営利性がグレーな場合は、事前に人事課などに確認しておくと安心です。
ケース②:教育・講演・執筆など公益性のある活動は認められることがある
教育や研究、講演、執筆活動など、社会的に意義のある「公益性の高い活動」は、一定の条件下で許可される可能性があります。
実際に、専門的な知識を活かして大学で非常勤講師を務めたり、本を執筆したりしている公務員も存在します。
これらの活動は、公務の信頼性や専門性を高める効果もあるため、自治体によっては積極的に支援する方針をとっているところもあります。
ただし、報酬が発生する場合は事前の許可が必要となるため、必ず申請手続きを行いましょう。
ケース③:自治体の許可を得れば一部の副業が可能になることがある
自治体によっては、副業に対する考え方や基準が少しずつ変わりつつあります。
特に地域活性化やスキル向上を目的とした副業に対しては、柔軟な対応を取るケースも見られます。
たとえば、空き家再生事業への参加や地域ビジネスの支援、資格を活かした講師活動などが、申請によって認められる場合があります。
ただし、副業の内容・時間・報酬の有無など、細かい審査項目があるため、正確な情報をもとに丁寧に申請することが大切です。
ケース④:ボランティアや地域活動は原則として制限されない
ボランティア活動や自治会・PTAなどの地域活動については、基本的に制限されていません。
これらは営利を目的としておらず、社会貢献や地域とのつながりを深める意味でも、地方公務員として積極的に関わることが推奨されています。
ただし、活動があまりにも過度になり、本業に支障をきたすようであれば、注意を受ける可能性もあります
勤務外であっても「職務専念義務」を意識し、バランスを保った関わり方が求められます。
副業がバレないために気をつけたい5つのポイント
副業が禁止されている立場でありながらも、生活費の補填や将来のために副収入を得たいと考える地方公務員の方は少なくありません。
しかし、副業がバレてしまえば懲戒処分の対象になる可能性もあるため、慎重な行動が求められます。
ここでは、副業がバレないために実際に気をつけるべき5つの重要なポイントをご紹介します。
ポイント①:住民税を「自分で納付」に設定すること
確定申告の際に最も重要なのが、「住民税の納付方法」です。
副業で得た収入を申告する際、「特別徴収(給与天引き)」ではなく「普通徴収(自分で納付)」に設定することで、勤務先に副業収入の情報が伝わるのを防ぐことができます。
この設定を忘れてしまうと、増加した住民税が給与に反映され、経理担当に怪しまれるリスクがあります。
確定申告書の「住民税に関する事項」の記載に十分注意しましょう。
ポイント②:本名や顔出しを避けて匿名で活動すること
副業を行う際は、できるだけ本名や顔写真を公開せず、匿名での活動を徹底することが基本です。
ブログ、YouTube、SNS、クラウドソーシングなど、ネット上では少しの情報から身元が特定されるリスクがあります。
とくに公務員という職業は地域に密着しているため、知人や住民に見つかる可能性もゼロではありません。
使用するハンドルネームやアイコンも、身近な人に結びつかないものを選ぶようにしましょう。
ポイント③:SNSで副業の内容を不用意に公開しないこと
「副業アカウント」として開設したSNSでも、思わぬ投稿から身元がバレることがあります。
写真に写り込んだ背景、投稿の時間帯、言葉遣いや話題の傾向などから、周囲に察知されてしまうことがあるため要注意です。
また、フォロワーや知人からの拡散によって、職場に情報が伝わるリスクもあります。
情報を発信する際は、「誰かが見ているかもしれない」という意識を常に持つことが大切です。
ポイント④:副業の時間帯や場所に注意して本業に支障を出さないこと
副業をする際に本業への影響が出てしまうと、「職務専念義務違反」として厳しく追及される可能性があります。
夜遅くまで作業して翌日の勤務に支障が出たり、職場の近くで副業をしていて見つかったりするケースも少なくありません。
自宅で完結する副業を選ぶ、週末や休暇中に限定するなど、時間と場所の管理を徹底しましょう。
体調管理にも気をつけて、常に本業を最優先する姿勢が求められます。
ポイント⑤:収入が増えても急激に生活レベルを変えないこと
副業でまとまった収入が入ると、つい生活レベルを上げたくなってしまうものです。
しかし、急に高価な物を買ったり、頻繁に旅行に出かけたりすると、周囲から不自然に思われることがあります。
特に同僚との会話の中で「そんな収入あるの?」と疑問を持たれると、副業の存在が浮上するきっかけになります。
生活水準はあくまで現状維持を心がけ、副収入は貯蓄や投資に回すとよいでしょう。
地方公務員の副業がバレた場合の処分内容と実際の事例
副業がバレた場合、地方公務員には厳しい処分が下される可能性があります。
「少しだけなら大丈夫」と軽く考えていた行為が、将来のキャリアや生活に大きな影響を与えることも。
ここでは、副業が発覚した場合に受ける可能性のある処分や、実際の事例について詳しく見ていきます。
戒告や減給などの懲戒処分を受ける可能性がある
副業が発覚した場合、まず考えられるのが「戒告」や「減給」などの懲戒処分です。
戒告はもっとも軽い処分とはいえ、正式な懲戒記録として残り、将来的な昇進や人事評価に影響を及ぼします。
減給処分になると、一定期間の給与が減額されるため、経済的なダメージも少なくありません。
たとえ副業が短期間だったとしても、「無許可」であれば処分対象となるため注意が必要です。
重い場合は停職や免職になるケースもある
副業の内容や規模、継続期間などによっては、より重い処分が科されることもあります。
実際に、長期間にわたって高額な報酬を得ていたり、本業に支障をきたしていた場合などは「停職」や「免職」に至るケースもあります。
特に、虚偽の報告や隠ぺい行為があった場合は、公務員としての信用を著しく損なうと判断され、厳罰の対象になりやすいです。
一度でも処分を受けてしまうと、その後の再就職にも悪影響を与えるため、リスクの大きさを十分に理解しておきましょう。
実際に処分された地方公務員の事例を紹介
たとえば、ある市役所職員が飲食店でアルバイトを続けていたことが発覚し、減給処分を受けた事例があります。
また、別の自治体では、動画投稿サイトで広告収入を得ていた職員が「副業禁止違反」として停職処分になったケースも。
これらの事例からわかるように、「小遣い稼ぎのつもりだった」「趣味の延長だった」という理由でも、営利性があれば処分の対象になります。
副業の内容に関係なく、ルール違反があれば厳正に対処されるという点は十分に理解しておきたいところです。
処分を受けた後のキャリアや生活への影響も大きい
懲戒処分を受けると、たとえ職場に残れたとしても、その後のキャリアには大きな影響が残ります。
昇進のチャンスを失うだけでなく、職場内での信頼関係が損なわれ、人間関係にストレスを抱えることも少なくありません。
また、免職となれば安定した収入を失い、再就職も難航する可能性があります。
公務員の身分を失うということは、退職金や年金、福利厚生などの面でも大きな損失を伴うため、「バレたときの代償」は極めて大きいといえるでしょう。
地方公務員の副業はバレない?許可制度とバレない対策についてまとめ
地方公務員にとって副業は、多くの制限がある一方で、生活や将来のために取り入れたいと考える人も増えています。
本記事では、副業がバレる理由やバレないための対策、許可が必要な活動、そして処分リスクについて網羅的に解説してきました。
副業を始める前には、「法律と自治体のルールを正しく理解すること」「リスクを見極めた行動をとること」が何よりも大切です。
必要に応じて人事課に相談する、または税務処理を慎重に行うなど、万全の準備を整えたうえで、自分の生活に合った方法を選んでいきましょう。
誰にも迷惑をかけず、自分の可能性を広げるための副業であるなら、ルールの範囲内で前向きにチャレンジしていくことが可能です。
リスクを正しく理解し、慎重かつ賢く行動することが、公務員の副業成功の鍵になります。
そしてもし「時間や場所に縛られず、継続的に収益を得られる副業」に関心がある方は、継続報酬型のWEBビジネスについてもチェックしてみると、新しい選択肢が広がるかもしれません。